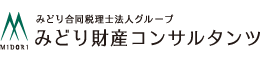2008年10月21日
事業承継の基礎の基礎 遺留分
こんにちは(^-^)/以前にブログでもご報告しましたが、事業承継セミナーをやっています。
僕が担当したのは「上手な経営承継法」ですが、内容は、中小企業経営承継円滑化法の民法特例についてのご紹介です。
中良企業経営承継円滑化法の民法特例は、中身は「遺留分」対策です。
セミナーのときも感じましたし、お客様とお話ししているときも感じるのですが、この「遺留分」について正しく理解していない方が多いのではないでしょうか。
「遺留分」は、相続人に保証された最低の取り分です。
相続事業総計対策のお話しになると、「最低これだけとれる」、「これだけ渡しとけばいいんでしょ」みたいな方向によくなります。
そうなのですが、それには大前提があります。
被相続人が「遺言」を作成しておかねばならないということです。
「遺言」があって、初めて「遺留分」の話しになるのです。
例えば、被相続人が相続人A、B、Cのうち相続人Aに財産すべてを相続させるという「遺言」を書いていたとします。
相続人Aは納得するでしょうが、相続人BやCはとても納得できないでしょう。
当然、相続人B、Cは相続人Aに対して財産の分け前を要求します。話し合いで解決できなければ、裁判所を通してのやりとりになります。このときに、相続人BやCの最低限の権利として守られるのが「遺留分」なのです。
例えば、被相続人が遺言を作らず死んでしまった場合、相続人A、B、Cは遺産分割協議を行うことになります。
話しがまとまらなければ、やはり裁判所を通して決着をつけますが、そのときの落ち着きどころは法定相続分となります。
「遺留分」は関係ありません。
中小企業経営承継円滑化法の民法特例は「遺留分」にフォーカスしています。
被相続人が生前に贈与した株式について、その株式を遺留分の計算の基礎から除外できる、もしくは、その株式を贈与時の価額で固定して遺留分の計算の基礎に算入できるという内容です。
ポイントは二つあります。
一つ目は、株式を生前贈与しなければならないことです。
二つ目は、遺留分なので、被相続人は遺言を作る必要があるということです。
基本的なことはきっちり押さえて、対策を検討、実行していきたいものですね
関連サービス
関連コラム
-
 事業承継 / 節税
事業承継 / 節税
2025.04.04
―会員限定―
オーナー社長必見!知っているようで知らない従業員持株会の基本の「き」(2025年3月26日開催) -
 事業承継 / 補助金・優遇税制
事業承継 / 補助金・優遇税制
2025.03.28
―会員限定―
【テキスト版】〜事業承継を考えるオーナー社長必見〜あと2年!100%納税猶予の◯と×(2025年2月27日開催) -
 事業承継
事業承継
2025.03.11
―会員限定―
〜事業承継を考えるオーナー社長必見〜あと2年!100%納税猶予の◯と×(2025年2月27日開催) -
 事業承継
事業承継
2025.02.26
―会員限定―
【テキスト版】オーナー社長が知っておきたい 2025年最新税財務情報セミナー ~知っている人が得をする~③ 2025年1月23日開催