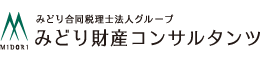2022年11月24日
令和5年度税制改正でいよいよ見直し!?相続・贈与の一体課税

11月も下旬となりました。来月12月には、与党の令和5年度税制改正大綱が公表されます。
ここ2年、導入が注目されている相続・贈与の一体課税ですが、今回の税制改正大綱では盛り込まれることになるのでしょうか?
これについて、自民党の宮沢洋一税制調査会長は、10月14日の日経新聞のインタビューで、「相続・贈与税の仕組みは2023年度改正で生前贈与の優遇を縮小する
制度に見直す」と発言しています。この発言からは、今回の税制改正大綱に相続・贈与の一体課税が何らかの内容で盛り込まれることになると考えられます。
現行、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造となっています。そのため、実際には、相続税かかからない者や多くの者に
とって、若年層への資産移転が進みにくくなっています。
その一方で、相続税がかかる者の中でも相続財産が多い一部の者にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低く、財産を分割して贈与する場合に、贈与税
の税率の方が相続税よりも低い税率が適用されます。
このような問題点から、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にするため、「資産移転の時期の選択により
中立的な税制」を構築するというのが、相続・贈与の一体課税です。
今月、11月8日には、第22回政府税制調査会が開催されましたが、そこでは、中期的な課題として、「わが国の場合は、法定相続分課税方式の下、贈与税・相続税が
別個の税体系となっているため、相続時精算課税制度は導入されているものの、こうした諸外国のように、贈与時点において課税関係が完結する形で累積的な課税を行う
ことは難しい。中期的に、こうした諸外国と同様の形で累積的な課税を目指すとすれば、法定相続分課税方式を見直していくことが考えられる。 」(下線は筆者)としています。

(出典:2022年11月8日第22回税制調査会説明資料)
また、当面の対応として、「現行の法定相続分課税方式の下での当面の対応としては、①相続時精算課税制度、②暦年課税における相続前贈与の加算、③経済対策等として時限的に
講じられている贈与税の非課税措置について検討することが考えられる。 」(下線は筆者)としています。
その上で、同日の税制調査会の専門家会合では、以下のような意見も出ております。
・暦年課税と相続時精算課税の選択制は引き続き維持した上で、課税の公平性を確保しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制である相続時精算課税制度の使い勝手を向上させ、
納税者が必要に応じて同制度を利用できるようにすべきではないか。
・暦年課税における相続前贈与の加算について、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築していく観点からは、諸外国の例も参考にしつつ、現行の加算期間を延ばすことが
適当ではないか。
・贈与税の非課税措置については、特に、教育資金や結婚・子育て資金に係る非課税措置については、制度創設当初と比べ、適用件数も大きく減少している。また、これらの措置で認
められてい使途については、近年、公費でカバーされる部分が増加している。相続時精算課税制度の使い勝手の向上と併せて、廃止する方向で検討することが適当ではないか。
上記からかは、中期的には、相続における現行の法定相続分課税方式を見直しを目指すが、当面は、法定相続分課税方式を維持しつつ、①相続時精算課税制度、②暦年課税における相続
前贈与の加算、③相続時精算課税の令和5年度の改正を行うことを検討していると考えられます。
具体的には、暦年課税と相続時精算課税の選択制を維持しつつ、相続時精算課税は利用しやすいものにし、暦年課税における相続前贈与の加算期間を3年から10年、もしくは15年にする
という改正、さらに、教育資金や結婚・子育て資金に係る非課税措置については廃止が、あくまで私見ですが、考えられそうです。
なお、適用時期については、過去の贈与に遡っての適用は難しいと考えられますが、改正内容ととともに、留意が必要です。